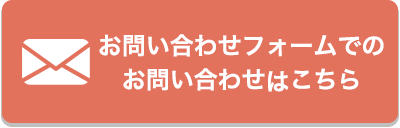医療過誤の事案概要
患者は糖尿病の持病があり、鍼灸院で左足底に針治療を行った後に、それが原因で感染症にかかってしまいました。感染の程度はひどく、左足底から左下腿にかけて皮膚の壊死や膿瘍形成、足の内部にガスの発生といった症状がみられました。治療としては、抗菌薬の投与に加え、皮膚を切開することにより排膿したり、壊死した皮膚を切除したりしていましたが、そのような治療を行っても完治することはできず、数か月にわたり入院ないし通院しながら治療を続けていました。そのような中、患者は熱を出し、左下肢のCT画像で筋肉内のガスが増加していたため、感染症の悪化により入院することになりました。入院後は抗菌薬による治療を受けていましたが、症状は徐々に増悪し、入院21日後に手術可能な病院に転院し、左下肢を膝から下で切断するという手術が行われました。
法律相談までの経緯
患者は、左下肢の感染に対して適切な治療が行われていたのか疑問に感じ、ある法律事務所に相談しました。弁護士を立てて病院に対して賠償を求めて交渉を行いましたが、話し合いでの解決に至りませんでした。そこで交渉を担当していた弁護士を通じて当事務所に相談がありました。
相談後の対応・検討内容
当事務所において、病院の診療録やCT画像の精査を行ったところ、患者は壊死性筋膜炎に罹患しており、早期に手術で壊死部分を除去していれば足を膝下から切断することはなかったという結論に至りました(皮膚表面部分の切除は行われていましたが、壊死は足の深部にまで達しており、そのような深部の部分の切除は行われていませんでした)。
壊死性筋膜炎とは
壊死性筋膜炎とは、浅層筋膜(皮膚の下の脂肪組織の中にある薄い筋肉の膜)を細菌感染の主座として急速に壊死が拡大する致死性の軟部組織感染症(脂肪や筋肉などにおける感染症)です。壊死性筋膜炎の中には、数時間で症状が進行していく劇症型のほか、数日間、場合によっては数週間かけて進行する亜急性の症例も存在します。壊死性筋膜炎の典型的な症状は、紅斑、紫斑、水疱、血疱、皮膚の壊死です。同じような症状をきたす疾患として蜂窩織炎(皮膚や皮下脂肪における感染症)との鑑別が問題となりますが、壊死性筋膜炎の方が進行が早く、より重症である傾向があります。壊死性筋膜炎を疑った場合、皮膚を切開し壊死組織を確認することにより診断に至ります。その際、壊死部分に白色混濁液が確認されることが多くみられます。
壊死性筋膜炎の診断に役立つものとして、「LRINECスコア」というものがよく知られています。これは血液検査を行い、CRP、白血球数、ヘモグロビン濃度、血清ナトリウム、 血清クレアチニン、 血糖の6項目について、それぞれの数値をスコア化し、 その合計が6点以上となる場合に壊死性筋膜炎の可能性が高いとされています。ただし、LRINECスコアが6点未満であっても壊死性筋膜炎を否定することはできません。
壊死性筋膜炎の治療にあたっては、できるだけ早期に外科的に壊死組織を除去する必要があります。壊死組織の除去は十分に行う必要があり、場合によっては1回目の手術の後に、壊死組織の残存がないか確認するため再度手術を行うこともあります。
臨床症状については、発熱や紅斑といった症状だけではなく水疱形成や皮膚壊死といった所見が認められると、壊死性筋膜炎の可能性も考えて慎重に判断する必要があります。また壊死性筋膜炎の場合、皮膚所見と内部の壊死の範囲が一致しないことがあり、皮膚所見が正常であるのに触ると痛みを訴えることがあります。皮膚の紅斑が急速に拡大する場合も壊死性筋膜炎を疑うべき経過で、敗血症性ショックなど重篤な症状が出現している場合も壊死性筋膜炎を見逃さないように気を付けなければなりません。CT画像所見に着目すると、今回のケースでは筋肉の間にガスが貯留していましたが、蜂窩織炎ではこのような所見はあまり見られません。次にLRINECスコアについてですが、6点以上になると壊死性筋膜炎の可能性が高くなると言われており、本件のようにLRINECスコアが8点以上の場合は壊死性筋膜炎の可能性を念頭において診療に当たる必要があります。
このように臨床症状、CT画像所見、LRINECスコアから壊死性筋膜炎の可能性を疑ったとしても、壊死性筋膜炎と診断するためには皮膚を切開し筋膜の壊死を確認する必要があります。壊死性筋膜炎の治療においては壊死組織の除去とともに抗菌薬投与も必要であり、感染している細菌の種類を同定するため血液培養を採取するとともに、壊死に伴う浸出液を皮膚切開の際に採取しておくことが治療に有用です。
弁護士の対応
話し合いでの解決には至らなかったため、病院に対して賠償を求め裁判をすることになりました。裁判においては、身体症状や血液検査、画像検査から、より早期に壊死性筋膜炎と診断し、壊死組織の完全除去を行うべきであったと患者側が主張したのに対し、病院側は、そもそも患者は壊死性筋膜炎ではなかったと反論し病院の責任を否定しました。また患者側が、早期に壊死性筋膜炎と診断し適切な治療を行っていれば左膝下での足切断を回避できたと主張したのに対し、病院側は、早期に壊死性筋膜炎に対する治療を行っていても足の切断は回避できなかったと反論しました。
患者の左下肢の状態が壊死性筋膜炎であったのかが争点となり、患者側病院側双方から医師の意見書を提出しました。患者側の意見書は下肢(膝が専門)の整形外科医と放射線科医2名の意見を得ることができました。左下肢のCT画像で深部に液体が貯留するともにガス像が見られることや、壊死性筋膜炎の指標となるLRINECスコアが8点以上となっていることから、患者は壊死性筋膜炎であるという意見を述べてもらいました。それに対して病院側からは整形外科医の意見書が提出され、それによれば、患者の臨床症状、血液検査、画像検査の結果を総合的に判断すると患者の左下肢の症状は壊死性筋膜炎ではなく蜂窩織炎(壊死組織の除去は不要)という意見でした。
このような両者の主張、意見書を踏まえ、裁判所から和解案が提示されました。患者が壊死性筋膜炎の状態にあったかという点について、CT画像所見から壊死性筋膜炎が疑われること、全身状態や血液検査について壊死性筋膜炎と考えてもおかしくないことから、患者は壊死性筋膜炎の状態にあり、早期に壊死組織を完全除去すべきであった、と過失(見落とし、診断の遅れ)は認められました。そのうえで治療が適切に行われていれば患者の膝下からの切断を回避できた相当程度の可能性があったと認められ、適切な治療を受けることができなかったことにつき慰謝料の請求が認められるべきであるから、数百万円程度が適当な金額だと説明を受けました。最終的にご依頼者と相談し、病院が患者に対して慰謝料を支払うという内容の和解が成立しました。
弁護士のコメント
今回のケースでは、壊死性筋膜炎と診断できるかが大きな争点になりましたが、実際の臨床現場でも壊死性筋膜炎と蜂窩織炎との鑑別にはしばしば難渋します。いずれの疾患も、皮膚の紅斑や疼痛といった症状をきたすものであり、そのような症状しかない症例の場合、壊死性筋膜炎と蜂窩織炎のいずれかであるか鑑別することは非常に重要です。なぜなら、蜂窩織炎の場合は抗菌薬投与で治療しますが、壊死性筋膜炎の場合は外科的手術が必要となり、治療方針が異なるからです。今回のケースでは特に、壊死性筋膜炎の中でも進行が比較的ゆっくりであったこともあり、患者側と病院側で意見が対立することになりました。
患者側からは筋肉や皮膚の中にガスがあるということが異常な状態であり、壊死性筋膜炎を示す所見だと主張し、整形外科専門医の先生も、放射線科医の先生方も同じ意見を述べておられました。客観的なCT画像所見という証拠もあったため、裁判所も見落としがあったことは認めてくれました。
しかし、患者さんには糖尿病があったことや、もともと足の指の一部が切断しなければならないような壊死もあったことなどから、たとえ早期発見をして治療をしたとしても膝下からの下肢切断を回避できたというところまではなかなか証明するのは難しいのではないか、というのが裁判所の見解でした。
たしかに、どのような状況で治療すれば下肢切断を回避できるのか、という点については、客観的な医学文献や証拠が少なく、既往症として糖尿病があると一定の割合で下肢切断を要するような感染を起こすこともある、という報告が多かったため、裁判を続けても、「下肢切断の回避」という因果関係の証明をすることは困難だと考えられました。その点も、依頼者と十分相談し、一定の割合で下肢切断が回避できたかもしれない、という意味の「相当程度の可能性があった」と考える裁判所の見解を受け入れ、裁判所からの提示金額での和解にすることとしました。
「相当程度の可能性」というのは、わかりにくい表現ですが、最高裁判所平成12年9月22日第二小法廷判決で示された考え方です。医療訴訟で、過失がなかったら結果(死亡や後遺症)がなかったはずだ、という因果関係を証明することは非常に難しいため、ある程度の可能性があれば一定割合の患者救済をしようという考え方に基づいた判決だと考えられています。
判決は、以下のようなものでした。
(つまり、因果関係の十分な証明はできていないけれども)
(つまり、適切な治療が行われたらある程度死んでいなかった可能性がある場合にも、ある程度の賠償を認めてあげよう、ということです。)
(理由として、命は重要であり、ある程度志望しなかった可能性があったような場合にも、賠償を認めてあげてもいいのではないか)
ただ、その金額は、本来の損害金額に比べると1割程度と低いもので、最高裁判決でも死亡事例だったにも関わらず200万円だけの賠償が認められました。
今回の和解もこの判決の考え方と同じような考え方である程度の可能性を認めてもらえたと考えられます。ご本人としては金額が少なく納得できないところもあったと思いますが、よく話し合い、最終的に和解することにしました。