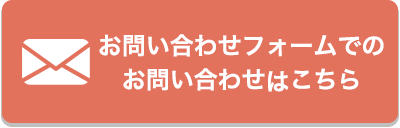外科手術の世界で、手術支援ロボットの「ダヴィンチ」の保険診療範囲が拡大し、全身の多くの外科手術で使用されるようになりました。ダヴィンチを使用した手術は、泌尿器科で先進的な取り組みとして始まり、前立腺がんや膀胱がん、腎臓がん、消化器外科の胃がん、食道がん、直腸がん、呼吸器外科の肺がん、産婦人科での子宮体がんなどで保険適用が認められることになり急速に拡大しています。
メリットは、患者さんが負担する医療費が、従来の腹腔鏡などの内視鏡を使った外科手術と同じままで、保険適用になり、これまでと同じ費用でより精度の高い手術を受けられる用になったということにあります。技術的にも、従来の腹腔鏡などよりも技術習得が早く、より精度の高い手術が実現可能とうたわれています。
今までの手術と何が違うのか、ロボットと言ってもどんなロボットが何をするのかイメージしにくいと思いますので、例えば、大腸がんの手術を例に説明しましょう。従来の直接お腹をメスで切って開く「開腹手術」では、医師は、患者さんの右側あるいは左側に立ち、メスで皮膚を切ってそこから両手をお腹の中に入れてがんの部分を切り取る手術をしていました。その後、お腹の傷を少しでも小さくし、手術後に患者さんが早く回復できるように、腹腔鏡というカメラが開発されました。腹腔鏡をつかった大腸癌の手術では、お腹に数cmの穴を開けて腹腔鏡という筒状のカメラを挿入し、カメラに写った画像を大きなモニターに映し出しながら、さらに小さな孔を1-2箇所開けて、その孔から長い柄のついたハサミやピンセットのようなはさむための器具(鉗子:かんし)を挿入してお腹の中のがんを切り取る手術です。外科医は、患者の右か左に立って、モニターの画像を見ながら、お腹の外で鉗子のハンドルを握ったり緩めたりして、長い柄の先端で操作をします。つまり、お腹の中には直接手を入れずに、細長い鉗子だけがお腹の中に入った状態で、手術を行う方法です。
腹腔鏡に引き続き、ロボット手術は、外科医が患者の横に立たず、患者とは離れたコックピットのような操作ボックスの中に座って、操作をすることが大きな違いです。患者さんのお腹の傷は、腹腔鏡のときと同じように数cmまでで、いくつか孔をあけ、孔の部分からロボットの手にあたる器具が、お腹の中に入ります。患者のお腹の中に挿入された器具は、ロボットのアーム(腕)といわれ、外科医の手の代わりに、このアームが患者さんの腸をさわり、がんを切除するのです。ロボットが勝手に手術を取ることはできませんので、コックピットに入っている外科医が、モニター画像を見ながらアームを操縦して、手術を行います。外科医は、患者さんの体に直接触れない、というのが最大の特徴です。モニター画像は、三次元で解像度の高い映像になり、その画像を見ながら外科医が手術を行うため、患者さんの体内に両手を入れて手術するような感覚で手術をすることが可能、といわれています。
ここまでの説明をすると、これまでの外科医による開腹手術と同じようなことが、ロボットのアームで可能になり、傷も小さいし良いことばかりのように思えます。しかし、実際には、ロボット手術の事故は跡を絶たず、出血による死亡が圧倒的に多いことが特徴です。なぜ、そんなことになるのか。外科医の技はART(芸術)ともいわれますが、それは、指先の感覚によって腸や脂肪、その間にあるごく薄い膜などを傷つけないで、悪いものだけを切り取る、その技術にあります。悪い部分を切ることはロボット・アームでも同じようにできます。しかし、生きている人間の体を切る、ということは、その部分に流れる血管を適切に切って縛り、残った正常な臓器が、手術後も正しく動くことが必要になる操作なのです。ロボット手術は、外科医が直接、患者さんの腸を触ることができません。硬さや厚みを感じることができず、外科医は触覚を使った操作ができないのです。3D画像は、進化して高解像度担ってきていますが、今のところ、外科医は、モニターに映る目で見た「視覚情報」だけをたよりにして、臓器の硬さや厚みを想像しながら手術をしなければならないのです。開腹手術であれば、外科医は、その指先の感覚と目で見た視覚情報をあわせて臓器の様子を観察しながら進めることができます。その時、人間の両手のちからは、握力や、指1本1本の力により、外科医は、各指を自由に使って、柔らかく臓器を持ち、正常な部分を損傷しないような丁寧な操作を行い、悪いところだけを取り除くのです。外科医の技術の高さは、正常な組織を傷つけずに悪いところだけを取り除けるか、というところにかかっています。ロボット手術では、柔らかい臓器をそっと傷つけないよう扱う、ということが難しいのです。ロボット・アームの動きは、外科医が操縦しますが、外科医の柔らかな手の動きをそのまま再現できるわけではありません。外科医は、悪いものをできるだけ徹底的に取り除く手術をしたいと考えます。お腹の中にがんが残らないよう、徹底的に。その点、今までの腹腔鏡では、先の長い棒をつかって、きれいに取り除けなかったところも、ロボット・アームなら自分の指のように挿入して取り除けるようになりました。そのため、これまで腹腔鏡などでは技術的に難しかった静脈周囲にあるリンパ節郭清(がんの周りにあるリンパ節を血管に沿って取り除いていく手術)を、積極的に血管ギリギリのところまで行えるようになったのです。
一方で、ロボット手術では、視覚情報しかないため、血管や脂肪の硬さを感覚的に知ることはできず、画像で見た情報をもとに、アームの力加減を間違って、力任せに操作をして血管を損傷してしまう、という事故が多発することになります。自分の手であれば、固くて脆いものなら柔らかく扱うことができる外科医も、ロボット手術では、思いの外強い力で操作してしまうことになり、正常な組織、特に血管損傷をしてしまう、ということに繋がりやすいのです。
ロボット手術の医療ミスの相談が増えて来たこともあり、全国の専門家のドクター達から色々なお話を聞かせていただいています。泌尿器科医・産婦人科医、消化器外科医、呼吸器外科医の診療科を問わず、どの先生とお話しても、ロボットは、外科医の指に比べてパワーがありすぎ、微妙で繊細な、外科医の指先の動きを再現するには相当の技術と慣れが必要だ、ということをおっしゃいます。これまで若手の育成に関わってこられた先生方ほど、これまでのロボット手術の問題点もよくご存じです。学会や研究会でもそのような視点から、執刀経験が豊富な医師を手術指導医(プロクター)として認定し、その指導者のもとで訓練する必要があるとされていますが、保険が適応になってから、急速に大病院から中規模病院までロボットが導入され、適切にロボットを扱える外科医の育成はまだまだ追いついていない現状があるようです。
さらに、ロボット支援システム「ダヴィンチ」は、そのシステム全体が数億円といわれ、手術を行うたびに使い捨ての特別な器具が必要です。1台の機会を導入すると年間維持費は数千万円、その維持費をまかなうためには、どんどん手術を行うことが必要、ということになります。
もう一つ、これまでの腹腔鏡手術では、腹腔鏡の器具メーカー複数がお互い切磋琢磨しより安全な器具を開発するという、患者さんにとって健全な技術開発が行われていました。ロボット手術は、現時点では「ダヴィンチ」の独占状態です。複数社で手術支援ロボットの開発が並行して進められていますが、今のところ、ダヴィンチに並ぶ機種はまだ開発されていません。全てのダヴィンチ手術の手術操作データを把握しているはずのメーカーは、事故症例を表に出すことはしないでしょう。これからもダヴィンチを使った手術をしたい外科医が、学会で「死亡事故」の報告を行うことも難しい状況があるでしょう。
このような色々な背景を持つロボット手術です。ロボット手術後の医療ミスの報道は、氷山の一角だと思います。ロボット手術での事故の報道を避けるために、示談で解決してしまえば、マスコミ報道されることはありません。そのような事故でなくなっている患者さんは数多くおられると推測します。
開腹手術から腹腔鏡手術に移行する時期にも、悲惨な事故は沢山起こりました。傷を小さくし術後の回復が早い、低侵襲手術が患者さんのためになることは明らかですし、これからも技術革新と外科医の技術向上によってよりよい手術が行われるようになるでしょう。しかし、その反面、トレーニング中の外科医による医療ミスで亡くなった患者さんやご遺族への救済も、同時にきちんと考える必要があります。これからロボット手術をしたいから、と医療ミスであることを隠し、仕方のない合併症だと説明して、泣き寝入りせざるをえないご遺族が多いのではないかと思います。「ロボット手術」「ダヴィンチ」の医療事故、というマスコミ報道を見るたび、外科医師の育成と同時に、外科医の経験不足、判断ミスで亡くなってしまった患者さんやご遺族には、正しく説明をすべきですし、帰ってこない大切な命にかえて、せめて補償をすべきだと通説に思います。