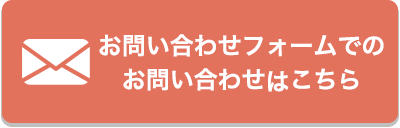医療ミスの事案概要
近畿地方の旧帝大附属病院で、当時30代の男性が髄膜腫のため、内視鏡下脳腫瘍摘出術を受けました。その際、執刀した医師は腫瘍周辺の正常な静脈を損傷し、その結果患者に静脈性脳梗塞が生じ、高次脳機能障害、右半身麻痺、失語症などの重い後遺症(障害等級1級)が残りました。
腫瘍は良性の髄膜腫で、内視鏡で手術をするには大きすぎる、といわれている大きさでしたが、医師は自信満々で、自分ならうまくできると説明していました。腫瘍は脳内の静脈に近接しており、重要な静脈を傷つけてしまうことを避けるためにも、腫瘍の一部を残してでも重要な静脈を温存すべきでした。
執刀した医師は、神経内視鏡の第一人者だと自ら語り、術前の説明でも危険な場合は無理はしないと話し、リスクを十分に把握しながら、腫瘍の摘出を試みた際に器具(バイポーラー)の先端が静脈にひっかかっている状態で、盲目的な操作を行って静脈を引き抜いて損傷し、
傷つけた血管を凝固処理している画像が残っていました。正常な静脈を凝固処理したことで血流が阻害され、静脈性脳梗塞を引き起こしたと考えられました。
裁判

裁判では、ビデオ画像に写っていた損傷された静脈が「視床線条体静脈」(脳の深部を走る血管)であるか、あるいは「腫瘍由来の静脈」であるかが主な争点となりました。
原告側は、複数の脳外科専門医の協力を得て、手術ビデオ・3DCT画像・MRI画像などの詳細な検討を重ね、損傷した静脈は明らかに「視床線条体静脈」であると主張しました。
病院側は、原告の主張に対し、都度反論を変えては、損傷した静脈が予想外に正常な血管とつながっていたものであり、処理すべき血管だったと主張しました。
証人尋問の実施も検討されましたが、最終的には、裁判所の勧めもあり(不本意ながら)1000万円の支払いを受ける内容での和解となりました。
弁護士のコメント
事故直後から静脈性梗塞であることに争いはありませんでしたが、相手方の医師は、ミスはしていない、処理すべき血管だったとの主張を繰り返していました。
裁判所は、当初、手術手技という専門的な判断を要するものであるため「鑑定」を実施したいとのことでしたが、本件訴訟当時、日本脳神経外科学会の理事長が被告病院の脳外科教授であり、学会推薦の鑑定人に公正公平な判断は不可能である旨を原告側からねばり強く伝え、
鑑定によらず原告側協力医と執刀医に手術ビデオを見せつつ対質とする尋問を行うべきだと主張しました。
担当した裁判長も原告主張の趣旨をくみとり、ビデオを共覧しながら、録画する方法での尋問を行おうと決めて準備をすすめていました。
その途中で、裁判長が交替することとなり、尋問前ではあるが、現時点での心証に基づき和解ができないか打診があり、紆余曲折の後、和解成立となりました。
和解の条件として、相手方の医師(訴訟中に被告病院の脳外科教授に就任)が、自らを被告とする訴え部分を取り下げなければ和解はしない、などと個人的なこだわりを主張したため、難航しましたが、
対抗条件として大学に対する和解条件から口外禁止条項を外すこと(つまり、和解解決について公表することができる条件)を求め、最終的に合意に至りました。
本件は、ビデオ画像で明らかに「静脈をひっかけている」にもかかわらず、何年間も事実を認めず、意味不明な主張を繰り返す医師の姿勢に怒りを超え呆れました。反省の姿勢も全くなく、最後まで自分は悪くないと言い張っていました。
一方で、ビデオ画像を左陪席とともに自ら見て検討しようとしていた裁判長に救われました。
このようなケースは、例えば交通事故ならドライブ・レコーダーがあれば解決する問題のはずです。それに比べ、医療訴訟では「正常な運転方法」にあたる「適切な手術手技」も原告が立証し、説明しなければならないという問題があります。最近は、ネット上でも手術ビデオ画像が多く公開されています。また、手術本にも、イラストだけでなくビデオ動画が添付されている教材が増えました。今後はもっと積極的にこれらを活用し、裁判所に「正常な運転方法」を伝えていく必要があると感じました。